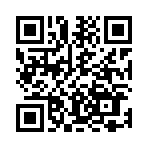2013年09月10日
防災・防犯まちづくり(防災活動発表会9/1)
防災・防犯まちづくり
『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)
9/1(日)
4.11:00~
救援・災害派遣
「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 「青木 泰憲 氏」
内容:東日本大震災における自衛隊の災害派遣数は計105800名であり、内訳は陸軍自衛隊70800名、海軍自衛隊14200名、空軍自衛隊21600名であった。自衛隊の被災地での業務は主に入浴支援、音楽による慰問、家族支援等、救援物資の荷分け配分、物資等輸送支援、行方不明者捜索に伴う瓦礫撤去の6種類に及ぶ。中でも、行方不明者捜索における瓦礫撤去作業は緊急性を要するものであり、常時活動する自衛官に加えて、予備自衛官も東日本大震災の際は配属されるほど、被害が甚大なものであった。
青木氏は自衛隊の在り方についても講じており、「我々自衛隊は、日向にでて称賛されることを望んではいけない。ただ無欲に被災者を助けることに遵守し、死を覚悟して業務を行うべきである」とのこと。自衛隊はサッカーでのゴールキーパーで、「日本国家の治安保持のための最後の砦として平時の訓練から緊張感を持ち行動する所存であります」という言葉で締めくくった。
5.13:00~
救命・救急医療
「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 「加藤 正哉 氏」
内容:災害医療は、「限られた医療資産の中で、最大多数の傷病者に最善を尽くす」ことが基本理念である。
平時の医療では、医師の需要量<医師の供給量であるが、一方災害時の医療では、医師の需要量>医師の供給量となり、一人の医師が多数の患者を診なければならない。そのため、災害時の医師は「一人の命より、二人の命を重きに置くといった冷静な判断を行わなければならない」。
災害医療の評価尺度は、回避できていたはずの死亡数/被災者で図ることができ、その死亡数を限りなく減らすことが理想である。
災害時により円滑に治療を行うためにも、医者は南海トラフ巨大地震に備ええ、日頃から災害時の医療についてシミュレーションしておく必要性があると同時に、一般の方も致命的な傷を避けるために「自助」について意識して貰いたい。
6.14:00~
救命・救急搬送
「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長 (消防司令長) 「和田 清 氏」
内容:阪神淡路大震災、東日本大震災の際における消防隊の救出活動や、被災者の死亡原因などのデータを和田氏は詳細に公表した。
阪神淡路大震災では6434人、東日本大震災では。20000人の死亡者数が記録されており、災害時の死亡原因として、地震発生後約14分後には91.9%の被災者が既死状態に陥り、「救出による救命率は極めて限られている」とも加藤氏は述べていた。
救出された人々の救出方法の割合は、「自助」「共助」の割合は98%、救助隊は1.7%になっており、「救命率を上げるためには、被災現場に最も近い人が積極的に助け合うことが必要である」とのこと。
以上の事により、今後の課題として、消防職員の安全確保の必要性についての周囲の理解、住民が自らの手で可能な自助の力を強化促進することが課題である。
7.15:00~
東日本大震災 復興支援
「東日本大震災 復興支援岩手県大槌町の現状と課題」

社会福祉コミュニティ総合事務所 代表・和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長さわやか福祉財団インストラクター近畿ブロック事務局長・NPO法人和歌山保健科学センター理事長 「市野 弘 氏」
内容:市野氏は岩手県大槌町の復興方針について、「ふれあい、ささえあい、たすけあい」の三点を述べていた。東北大震災が起こり、大槌町建物は崩壊し、物はなにもなくなった。しかし、東北の人々は立ち直りが早く、震災から三か月しか経過していないにも関わらず、被災地で「パラソル喫茶」という喫茶店をオープンし、東北に活気を与えている。また、「新生おおつち」という住民団体を立ち上げる等、復興に向けて一致団結して歩き始めている。
市野氏の講演は、アクティブラーニングの形式をとっており、講演を聞いていた人たちも様々な地位の人になりきって、防災ついての考えを客観的に考えた。講演会を聞いた後の人達は、「防災についての考え方は土地柄や境遇等、その人が置かれている環境について変わっていくものであるのだなと感じた」や、「防災について深く考えさせられた」と述べており、皆講演会の内容の濃さに圧倒されているようだった。
≪会場風景≫

1日目に引き続き、多くの発表をすべて聴講する参加者もおられました。
4人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。
『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)
9/1(日)
4.11:00~
救援・災害派遣
「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 「青木 泰憲 氏」
内容:東日本大震災における自衛隊の災害派遣数は計105800名であり、内訳は陸軍自衛隊70800名、海軍自衛隊14200名、空軍自衛隊21600名であった。自衛隊の被災地での業務は主に入浴支援、音楽による慰問、家族支援等、救援物資の荷分け配分、物資等輸送支援、行方不明者捜索に伴う瓦礫撤去の6種類に及ぶ。中でも、行方不明者捜索における瓦礫撤去作業は緊急性を要するものであり、常時活動する自衛官に加えて、予備自衛官も東日本大震災の際は配属されるほど、被害が甚大なものであった。
青木氏は自衛隊の在り方についても講じており、「我々自衛隊は、日向にでて称賛されることを望んではいけない。ただ無欲に被災者を助けることに遵守し、死を覚悟して業務を行うべきである」とのこと。自衛隊はサッカーでのゴールキーパーで、「日本国家の治安保持のための最後の砦として平時の訓練から緊張感を持ち行動する所存であります」という言葉で締めくくった。
5.13:00~
救命・救急医療
「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 「加藤 正哉 氏」
内容:災害医療は、「限られた医療資産の中で、最大多数の傷病者に最善を尽くす」ことが基本理念である。
平時の医療では、医師の需要量<医師の供給量であるが、一方災害時の医療では、医師の需要量>医師の供給量となり、一人の医師が多数の患者を診なければならない。そのため、災害時の医師は「一人の命より、二人の命を重きに置くといった冷静な判断を行わなければならない」。
災害医療の評価尺度は、回避できていたはずの死亡数/被災者で図ることができ、その死亡数を限りなく減らすことが理想である。
災害時により円滑に治療を行うためにも、医者は南海トラフ巨大地震に備ええ、日頃から災害時の医療についてシミュレーションしておく必要性があると同時に、一般の方も致命的な傷を避けるために「自助」について意識して貰いたい。
6.14:00~
救命・救急搬送
「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長 (消防司令長) 「和田 清 氏」
内容:阪神淡路大震災、東日本大震災の際における消防隊の救出活動や、被災者の死亡原因などのデータを和田氏は詳細に公表した。
阪神淡路大震災では6434人、東日本大震災では。20000人の死亡者数が記録されており、災害時の死亡原因として、地震発生後約14分後には91.9%の被災者が既死状態に陥り、「救出による救命率は極めて限られている」とも加藤氏は述べていた。
救出された人々の救出方法の割合は、「自助」「共助」の割合は98%、救助隊は1.7%になっており、「救命率を上げるためには、被災現場に最も近い人が積極的に助け合うことが必要である」とのこと。
以上の事により、今後の課題として、消防職員の安全確保の必要性についての周囲の理解、住民が自らの手で可能な自助の力を強化促進することが課題である。
7.15:00~
東日本大震災 復興支援
「東日本大震災 復興支援岩手県大槌町の現状と課題」

社会福祉コミュニティ総合事務所 代表・和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長さわやか福祉財団インストラクター近畿ブロック事務局長・NPO法人和歌山保健科学センター理事長 「市野 弘 氏」
内容:市野氏は岩手県大槌町の復興方針について、「ふれあい、ささえあい、たすけあい」の三点を述べていた。東北大震災が起こり、大槌町建物は崩壊し、物はなにもなくなった。しかし、東北の人々は立ち直りが早く、震災から三か月しか経過していないにも関わらず、被災地で「パラソル喫茶」という喫茶店をオープンし、東北に活気を与えている。また、「新生おおつち」という住民団体を立ち上げる等、復興に向けて一致団結して歩き始めている。
市野氏の講演は、アクティブラーニングの形式をとっており、講演を聞いていた人たちも様々な地位の人になりきって、防災ついての考えを客観的に考えた。講演会を聞いた後の人達は、「防災についての考え方は土地柄や境遇等、その人が置かれている環境について変わっていくものであるのだなと感じた」や、「防災について深く考えさせられた」と述べており、皆講演会の内容の濃さに圧倒されているようだった。
≪会場風景≫

1日目に引き続き、多くの発表をすべて聴講する参加者もおられました。
4人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。
Posted by 守ろう、わかやま at 20:01│Comments(0)
│NPO(特定非営利活動法人) 震災から命を守る会