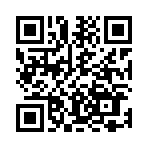2013年09月10日
防災・防犯まちづくり(防災活動発表会8/31)
防災・防犯まちづくり
『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)
8/31(土)
1.11:00~
防犯・治安対策
「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策‐東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から‐」

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 「岡本 葉子氏」
内容:阪神淡路大震災での、女性の死亡者数は、男性の死亡者数より1000人も多い。この原因として、男性の女性に対する、性的暴力、身体的暴力が原因の一部である。また、震災後の復興の方針など決める際の地方防災会議では、男性の参加者がほとんどであり、女性の意見が反映さる機会がなかった。偏見した考え(女性は家事洗濯、男は仕事といった)を持った男性の考え方を変えていかなければならない。
被災地では「それぞれの特性を生かした災害時の役割分担が重要」であり、そのためにもより女性の防災への関与が不可欠である。
男女共同参画センターでは、女性だけで会議を行う機会を設け、従来の参加者のほとんどが男性という地方防災会議の際に反映されなかった女性の意見を出来るだけ反映させようと現在も活動を続けている。
2.14:00~
防災・減災・復興
「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

和歌山県 新宮市市長 「田岡 実千年 氏」
内容:新宮市は和歌山県の紀南に位置し南海トラフ大震災での甚大な津波の被害が予想される市である。新宮市長田岡氏は、「公助」、「共助」の両面からの防災対策を行っている。
「公助」としては、津波の被害軽減のために、大浜堤防(2次防衛ライン)緑地の設置がある。これは、逃げる高台の確保と被災後の仮設住宅用地の確保を目標に設置されている。
「共助」の強化方法としては、「若者を呼びこむことが、防災にもつながる」ことが挙げられる。「力強いふるさと振興」を基本理念に、地域活力を再生する手立てとして、田舎暮らしをしたいと考えている若者を集っての地域おこし協力隊という隊員を3名募集し、結果26名の応募者が集まった。しかし、あくまでも、「自分の身は出来る限り自分で守るべきである」というのが和田氏の意見であり、「自助」の強化こそが最重要なのである。
3.15:30~
紀伊半島豪雨 復興支援
「学生の被災地支援活動‐紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み‐」

和歌山大学 災害ボランティアチーム FORWARD
代表 「中村 勇太郎 氏」
内容:和歌山大学観光学部3回生の中村勇太郎氏は、昨年から現在まで行っている活動として3つの活動の報告をした。災害ボランティアチームFORWARDの活動としては、①災害ボランティアバス②写真修復プロジェクト③近露基地道補修ボランティアの3つが挙げられる。
①の災害ボランティアバスでは、和歌山県の新宮市、岩手県の釜石市の二県を訪れ、震災被害者の座談会や、震災により荒れた道路の補修を行った。
②の写真修復プロジェクトでは、震災により汚れてしまった写真を、修理、加工を行い、きれいな状態で所持者に渡した。この写真プロジェクトは、「現地に行かなくても行えるボランティア」という新しい形のボランティアであり、「平時的に災害ボランティアを行っていきたい」という中村 勇太郎氏の思いが詰まったプロジェクトである。
③の近露基地プロジェクトでは、空き家を宿泊施設にし、それを起点として和歌山県南部の道の補修を行った。空き家を放置することにより起こる建物の老朽化を防ぎ、震災後の建物の崩壊という二次災害も防ぐことも、このプロジェクトの目的である。
≪会場風景≫

参加した方々は熱心に聞き入り、積極的に質問する姿も見られました。
3人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。
『命を守るための防災活動発表会』9/2(日)へと続きます。
『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)
8/31(土)
1.11:00~
防犯・治安対策
「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策‐東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から‐」

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 「岡本 葉子氏」
内容:阪神淡路大震災での、女性の死亡者数は、男性の死亡者数より1000人も多い。この原因として、男性の女性に対する、性的暴力、身体的暴力が原因の一部である。また、震災後の復興の方針など決める際の地方防災会議では、男性の参加者がほとんどであり、女性の意見が反映さる機会がなかった。偏見した考え(女性は家事洗濯、男は仕事といった)を持った男性の考え方を変えていかなければならない。
被災地では「それぞれの特性を生かした災害時の役割分担が重要」であり、そのためにもより女性の防災への関与が不可欠である。
男女共同参画センターでは、女性だけで会議を行う機会を設け、従来の参加者のほとんどが男性という地方防災会議の際に反映されなかった女性の意見を出来るだけ反映させようと現在も活動を続けている。
2.14:00~
防災・減災・復興
「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

和歌山県 新宮市市長 「田岡 実千年 氏」
内容:新宮市は和歌山県の紀南に位置し南海トラフ大震災での甚大な津波の被害が予想される市である。新宮市長田岡氏は、「公助」、「共助」の両面からの防災対策を行っている。
「公助」としては、津波の被害軽減のために、大浜堤防(2次防衛ライン)緑地の設置がある。これは、逃げる高台の確保と被災後の仮設住宅用地の確保を目標に設置されている。
「共助」の強化方法としては、「若者を呼びこむことが、防災にもつながる」ことが挙げられる。「力強いふるさと振興」を基本理念に、地域活力を再生する手立てとして、田舎暮らしをしたいと考えている若者を集っての地域おこし協力隊という隊員を3名募集し、結果26名の応募者が集まった。しかし、あくまでも、「自分の身は出来る限り自分で守るべきである」というのが和田氏の意見であり、「自助」の強化こそが最重要なのである。
3.15:30~
紀伊半島豪雨 復興支援
「学生の被災地支援活動‐紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み‐」

和歌山大学 災害ボランティアチーム FORWARD
代表 「中村 勇太郎 氏」
内容:和歌山大学観光学部3回生の中村勇太郎氏は、昨年から現在まで行っている活動として3つの活動の報告をした。災害ボランティアチームFORWARDの活動としては、①災害ボランティアバス②写真修復プロジェクト③近露基地道補修ボランティアの3つが挙げられる。
①の災害ボランティアバスでは、和歌山県の新宮市、岩手県の釜石市の二県を訪れ、震災被害者の座談会や、震災により荒れた道路の補修を行った。
②の写真修復プロジェクトでは、震災により汚れてしまった写真を、修理、加工を行い、きれいな状態で所持者に渡した。この写真プロジェクトは、「現地に行かなくても行えるボランティア」という新しい形のボランティアであり、「平時的に災害ボランティアを行っていきたい」という中村 勇太郎氏の思いが詰まったプロジェクトである。
③の近露基地プロジェクトでは、空き家を宿泊施設にし、それを起点として和歌山県南部の道の補修を行った。空き家を放置することにより起こる建物の老朽化を防ぎ、震災後の建物の崩壊という二次災害も防ぐことも、このプロジェクトの目的である。
≪会場風景≫

参加した方々は熱心に聞き入り、積極的に質問する姿も見られました。
3人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。
『命を守るための防災活動発表会』9/2(日)へと続きます。
Posted by 守ろう、わかやま at 20:00│Comments(0)
│NPO(特定非営利活動法人) 震災から命を守る会