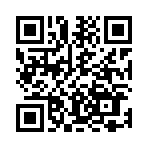2016年04月24日
熊本地震
熊本地震
謹んで 熊本県熊本地方を震源地とする「熊本地震」によって、熊本県、大分県、周辺の皆様でお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
熊本地震 (4月14日(木)21時26分) が発生して、10日が経ちました。
震度7クラスの大型地震が二度起こるという、自然の驚異をあからさまに見せつけられた震災でした。気象庁は最初の地震を「前震」、28時間後の4月16日(土)1時25分に起きた地震を「本震」と後日発表しました。 私は、14日に発生した地震の後に、“もっと大きな地震が発生する可能性がある”ということを、地震で被災されている方々に対して辛い時に伝えるのは酷かも知れませんが、命を守るための警告として、“しかるべきところ”が周知すべきであったと思います。
過去に発生した地震データには、本震の前に、それなりの規模の地震が発生しているということが解明されています。
地震科学者や専門家ならご存知の知識であり、専門用語かも知れませんが、これまでの震災で「前震」「本震」という言葉で地震を表現されたことは耳にしません。ましては、地震の少ない九州地方の皆さんには、本震も前震も即座に何らかの方法で伝えてもらわなくては、わかることがありません。
思い起こせば、5年前に発生した東日本大震災では、津波は一度だけでなく、何度も東日本の海岸に押し寄せたのではなかったでしょうか。
津波の発生するメカニズムは、海底で起こる地震や火山活動であり、それによって海底での地滑り等が二次的に発生することによって、
水の塊は複数にわたって何度も形を変え、津波となって陸に遡上する自然現象といわれています。津波の大きさ、速さというのはそれぞれ違うのでしょうが、大小形を変えて水は波となって陸を襲います。
これに平行して、海底で起こる地震や火山活動が起こるたびに陸が揺れるという仕組みです。ですので、東日本大震災では、陸が何度も揺れた後に、津波が何度も押し寄せたというわけです。
東日本大震災の場合は海底で起こる海溝型地震=津波発生というパターンでしたが、陸内の直下で発生する直下型地震も、一度だけでなく、何度も地震を繰り返します。それが余震というわれるものですが、小さいのもあれば、大きいのもあります。この余震の怖さを、もっと詳しく、命にかかわる情報として知らされていなかったことが、悔やまれてなりません。
当会は、阪神淡路大震災によって被災した故岩瀧幸則氏によって、
震災を予防するNPOとして立ち上げられました。災害後のボランティアを活動とする組織ではなく、命を守るために、平素何を準備すべきか、何をするべきかをお伝え、お手伝いする組織です。なのに、余震のメカニズム、それ周知をする力、知識、方法等が未熟です。繰り返しますが、悔やまれてなりません。
“しかるべきところ”の責任にして終わってははならない、私どもの存在、意義のあり方を見直さなければならない。猛省です。 私は、災害対策の原則として「準備していないことは、“いざ”という時にできない」と考えています。だからこそ、事前予防の対策、心構えと実践が必要なのです。予防に勝る治療はありません。
当会は、微力弱小の組織ではありますが、「命を守る」ための事前予防対策を啓蒙する組織として、大いに反省し、改めて努めて参る所存です。
今、熊本県、大分県では、お亡くなりになった方のご家族、命はとりとめたが様態が重く入院されいる方、入院はしていないがエコノミー症候群の兆候のある方、身体は元気でも職場が崩壊してどうすれば悩まれている方等々、様々な方が辛い思いをされています。
しかし、不通だった交通網も復旧し、離れ離れとなっていた家族との再会が実現されている方もあり、少しずつ明るさを取り戻す流れが出だしていることに気持ちが和みます。そして全国、いや世界中からボランティアの皆さんが被災地のお手伝いに迎えるようになりました。問題点として、避難所によって物資、ボランティアの配分がうまくいかず、その格差が出てきているところもあるようです。こうした点は、被災後の課題として考えていかねばならないでしょう。
でも、それは命があってこそ、辛くも耐えていかねばならない試練だと思います。生意気で失礼な表現かも知れませんが、「自分の命があってこそ」です。
驚かせるわけではありませんが、次の震災、災害に備えることを忘れてはいけません。命を脅かす災害は、今日起こるかもしれないのですから・・・。
平成28年4月24日
特定非営利活動法人
震災から命を守る会
理事長 臼井康浩
今、熊本県、大分県では、お亡くなりになった方のご家族、命はとりとめたが様態が重く入院されいる方、入院はしていないがエコノミー症候群の兆候のある方、身体は元気でも職場が崩壊してどうすれば悩まれている方等々、様々な方が辛い思いをされています。
しかし、不通だった交通網も復旧し、離れ離れとなっていた家族との再会が実現されている方もあり、少しずつ明るさを取り戻す流れが出だしていることに気持ちが和みます。そして全国、いや世界中からボランティアの皆さんが被災地のお手伝いに迎えるようになりました。問題点として、避難所によって物資、ボランティアの配分がうまくいかず、その格差が出てきているところもあるようです。こうした点は、被災後の課題として考えていかねばならないでしょう。
でも、それは命があってこそ、辛くも耐えていかねばならない試練だと思います。生意気で失礼な表現かも知れませんが、「自分の命があってこそ」です。
驚かせるわけではありませんが、次の震災、災害に備えることを忘れてはいけません。命を脅かす災害は、今日起こるかもしれないのですから・・・。
平成28年4月24日
特定非営利活動法人
震災から命を守る会
理事長 臼井康浩
Posted by 守ろう、わかやま at 10:53│Comments(0)
│NPO(特定非営利活動法人) 震災から命を守る会